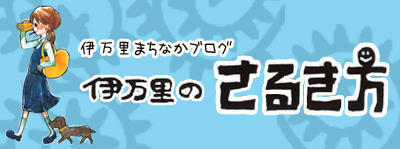2011年02月27日
未だ着雪中!
伊万里弁で語るバイのブログ
土曜日(2/26)に三瀬峠ば通ったぎ・・・こげな風景が・・・

進めば進むぎ雪の量が増えて来て・・・


佐賀側かい県境ば越えるぎ雪の量が格段に増えた・・・
やっぱい如月は・・・まだまだ、冬!

進めば進むぎ雪の量が増えて来て・・・


佐賀側かい県境ば越えるぎ雪の量が格段に増えた・・・
やっぱい如月は・・・まだまだ、冬!
2010年11月16日
横綱 白鵬関 連勝止まる
伊万里弁で語るバイのブログ
昨日、家に帰ってTVば点けたら丁度NHKのニュースで
「白鵬 連勝止まる!」って言葉に思わず「なんやてッ!?」と
独りツッコミ・・・
相手が個人的に好いとぉ稀勢の里関やったけん何か複雑な気分・・・
元横綱 千代の富士、現在の九重部屋 親方の云いよらしたばってん
「連勝というのは、いつかは止まる。白鵬はまだ若いし、ほかの力士との差もある。まだまだ時代は続く」
って事は、双葉山が69連勝の止まった後に31歳で4連覇、36連勝したこつば考えっぎんた
25歳の白鵬関・・・70連勝越えはありあえる話し・・・ですたいねぇ~
「白鵬 連勝止まる!」って言葉に思わず「なんやてッ!?」と
独りツッコミ・・・
相手が個人的に好いとぉ稀勢の里関やったけん何か複雑な気分・・・
元横綱 千代の富士、現在の九重部屋 親方の云いよらしたばってん
「連勝というのは、いつかは止まる。白鵬はまだ若いし、ほかの力士との差もある。まだまだ時代は続く」
って事は、双葉山が69連勝の止まった後に31歳で4連覇、36連勝したこつば考えっぎんた
25歳の白鵬関・・・70連勝越えはありあえる話し・・・ですたいねぇ~
2010年10月10日
正しい伊万里弁の使い方講座⑭
伊万里弁で語るバイのブログ
今日は、最終回です。
これまで、お付き合いいただきましてありがとうございました。
14回までトータルで呼んでいただければ、かなり伊万里弁のことが分かっていただいたと思います。
①~⑭まで掲載した内容は、すべて伊万里コンシェルジェ検定新テキストに掲載予定です。
ご希望の方は、11月1日より無料で配布予定です。
また、ホームページからもダウンロード出来るようにいたします。
【いまりのことば】②
「~だから」は「~じゃーけん(佐賀方言)」「~じっゃけん(伊万里町とその周辺(しゅうへん))」「~じゃるけん(唐津方言)」というように、地域によって言い方が少し違ってきます。
「~しに行く」というのは「~しぎゃーいく」といいます。
「~すれば」「~したら」は「~すっぎー」「~したいぎー」「~すっぎにゃーと」といいます。
「それでは」は「そいぎー」といいます。
「しかし」や「けれども」は「ばってん」や「あいどん」・「ないどん」といいます。それぞれ「ばとても」「あれども」「なれども」という古語(こご)が変化(へんか)したことばです。
「こんな(に)」「そんな(に)」「あんな(に)」「どんな(に)」は「佐賀方言:こがん(唐津方言:こぎゃん)」「そがん(そぎゃん)」「あがん(あぎゃん)」「どがん(どぎゃん)」。
黒川町(くろかわちょう)の一部(いちぶ)では「こやん」「そやん」ともいいます。「どれほど⇒どがしこ」のように、量をあらわす「~しこ」「~しこら」ということばもあります。
伊万里市のことばのアクセントについては、まだ十分(じゅうぶん)に研究(けんきゅう)されていませんが、大体(だいたい)、唐津方言で一型(いちかた)アクセント(アクセントがはっきりしない)に、佐賀方言は二型(にかた)アクセント(アクセントがはっきりしている)に入(はい)るといわれています。
佐賀方言と唐津方言が、ひどく違うことばのように聞(き)こえるのはこのことによるものでしょう。
以上でおしまい。
伊万里弁検定試験?を検討中です?
①~⑭まで、読んでいただいたあなたには、無条件で伊万里弁検定4級を進呈いたします?
3級以上につきましては、筆記試験(標準語訳・単語・伊万里弁の作文など)?を予定しています??
あなたも、伊万里弁をマスターして、楽しい伊万里弁ライフを楽しみましょう!!
※おことわり:伊万里弁検定の開催はあくまでも構想で、未定です。

これまで、お付き合いいただきましてありがとうございました。
14回までトータルで呼んでいただければ、かなり伊万里弁のことが分かっていただいたと思います。
①~⑭まで掲載した内容は、すべて伊万里コンシェルジェ検定新テキストに掲載予定です。
ご希望の方は、11月1日より無料で配布予定です。
また、ホームページからもダウンロード出来るようにいたします。
【いまりのことば】②
「~だから」は「~じゃーけん(佐賀方言)」「~じっゃけん(伊万里町とその周辺(しゅうへん))」「~じゃるけん(唐津方言)」というように、地域によって言い方が少し違ってきます。
「~しに行く」というのは「~しぎゃーいく」といいます。
「~すれば」「~したら」は「~すっぎー」「~したいぎー」「~すっぎにゃーと」といいます。
「それでは」は「そいぎー」といいます。
「しかし」や「けれども」は「ばってん」や「あいどん」・「ないどん」といいます。それぞれ「ばとても」「あれども」「なれども」という古語(こご)が変化(へんか)したことばです。
「こんな(に)」「そんな(に)」「あんな(に)」「どんな(に)」は「佐賀方言:こがん(唐津方言:こぎゃん)」「そがん(そぎゃん)」「あがん(あぎゃん)」「どがん(どぎゃん)」。
黒川町(くろかわちょう)の一部(いちぶ)では「こやん」「そやん」ともいいます。「どれほど⇒どがしこ」のように、量をあらわす「~しこ」「~しこら」ということばもあります。
伊万里市のことばのアクセントについては、まだ十分(じゅうぶん)に研究(けんきゅう)されていませんが、大体(だいたい)、唐津方言で一型(いちかた)アクセント(アクセントがはっきりしない)に、佐賀方言は二型(にかた)アクセント(アクセントがはっきりしている)に入(はい)るといわれています。
佐賀方言と唐津方言が、ひどく違うことばのように聞(き)こえるのはこのことによるものでしょう。
以上でおしまい。

伊万里弁検定試験?を検討中です?
①~⑭まで、読んでいただいたあなたには、無条件で伊万里弁検定4級を進呈いたします?
3級以上につきましては、筆記試験(標準語訳・単語・伊万里弁の作文など)?を予定しています??
あなたも、伊万里弁をマスターして、楽しい伊万里弁ライフを楽しみましょう!!
※おことわり:伊万里弁検定の開催はあくまでも構想で、未定です。
2010年10月10日
正しい伊万里弁の使い方講座⑬
伊万里弁で語るバイのブログ
今日も伊万里弁をマスターしましょう
【いまりのことば】編①
伊万里市内(いまりしない)で話(はな)されていることばは大(おお)きく分(わ)けて佐賀方言(さがほうげん)と唐津(からつ)方言があります。
そしてそれがつかわれる地域(ちいき)のなかでも地区(ちく)によって少(すこ)し違(ちが)うことばもあります。
しかし、どちらも同(おな)じ肥(ひ)筑(ちく)方言(ほうげん)に属(ぞく)しているので、全(ぜん)体(たい)的(てき)には共(きょう)通(つう)することばが多(おお)くあります。
伊万里市のことばの特(とく)色(しょく)を知(し)るために、少し例(れい)をあげてみましょう。
「おお」や「おう」は「うー」になることが多く、「大水(おおみず)⇒うーみず」「大事(おおごと)⇒うーごと」「追(お)うてくる⇒うーてくっ(唐津方言:おうちくる)」。
「よう」は「ゆー」になります。
「用事(ようじ)⇒ゆうじ」「良(よ)くない⇒ようなか⇒ゆーなか」。
ただし、「大分県(おおいたけん)」「土曜日(どようび)」などは音(おと)が変(か)わりません。
「あい」は「やー」になります。
「愛(あい)らしい⇒やーらしか」「書(か)いた⇒きゃーた」「大工(だいく)⇒佐賀方言:じゃーく(唐津(からつ)方言(ほうげん):でゃーく)」。
「おい」は「うぇー」か「えー」になります。「甥(おい)⇒うぇー」「後(あと)追(お)い⇒あとうぇー・あとえー」。
「すい」は「しー」か「すぃー」になります。「西瓜(すいか)⇒しーか・すぃーか」「吸(す)いつく⇒しーつく・すぃーつく」。
「来(く)る⇒くっ」「する⇒すっ」「負(ま)ける⇒負(ふ)くっ」などは語尾(ごび)がつまります。
「買(か)った⇒こーた」「借(か)りた⇒かった」は西日本(にしにっぽん)ではよくいわれますが、伊万里市も例外(れいがい)ではなく、「買って⇒こーて(唐津方言では「こーち」)」。
「うれっしゃあする」などのように「~がる」というところを「~さにする」といいます。
「~できる」は「~しきる」「~しゆっ」、「~できない」は「~しきらん」「~しえん」といいます。
つづく

【いまりのことば】編①
伊万里市内(いまりしない)で話(はな)されていることばは大(おお)きく分(わ)けて佐賀方言(さがほうげん)と唐津(からつ)方言があります。
そしてそれがつかわれる地域(ちいき)のなかでも地区(ちく)によって少(すこ)し違(ちが)うことばもあります。
しかし、どちらも同(おな)じ肥(ひ)筑(ちく)方言(ほうげん)に属(ぞく)しているので、全(ぜん)体(たい)的(てき)には共(きょう)通(つう)することばが多(おお)くあります。
伊万里市のことばの特(とく)色(しょく)を知(し)るために、少し例(れい)をあげてみましょう。
「おお」や「おう」は「うー」になることが多く、「大水(おおみず)⇒うーみず」「大事(おおごと)⇒うーごと」「追(お)うてくる⇒うーてくっ(唐津方言:おうちくる)」。
「よう」は「ゆー」になります。
「用事(ようじ)⇒ゆうじ」「良(よ)くない⇒ようなか⇒ゆーなか」。
ただし、「大分県(おおいたけん)」「土曜日(どようび)」などは音(おと)が変(か)わりません。
「あい」は「やー」になります。
「愛(あい)らしい⇒やーらしか」「書(か)いた⇒きゃーた」「大工(だいく)⇒佐賀方言:じゃーく(唐津(からつ)方言(ほうげん):でゃーく)」。
「おい」は「うぇー」か「えー」になります。「甥(おい)⇒うぇー」「後(あと)追(お)い⇒あとうぇー・あとえー」。
「すい」は「しー」か「すぃー」になります。「西瓜(すいか)⇒しーか・すぃーか」「吸(す)いつく⇒しーつく・すぃーつく」。
「来(く)る⇒くっ」「する⇒すっ」「負(ま)ける⇒負(ふ)くっ」などは語尾(ごび)がつまります。
「買(か)った⇒こーた」「借(か)りた⇒かった」は西日本(にしにっぽん)ではよくいわれますが、伊万里市も例外(れいがい)ではなく、「買って⇒こーて(唐津方言では「こーち」)」。
「うれっしゃあする」などのように「~がる」というところを「~さにする」といいます。
「~できる」は「~しきる」「~しゆっ」、「~できない」は「~しきらん」「~しえん」といいます。
つづく

タグ :伊万里ふるさと読本より伊万里弁
2010年10月09日
正しい伊万里弁の使い方講座⑫
伊万里弁で語るバイのブログ
今日も正しい伊万里弁をマスターしましょう
【むかしことば】編
「セ」を「シュ」と発音(はつおん)する人(ひと)は、だんだん少(すく)なくなりましたが、まだ、伊万里市(いまりし)の中高年(ちゅうこうねん)の人には、そう発音する人がいます。
九州地方(きゅうしゅうちほう)の人に特有(とくゆう)の発音といいますが、室町(むろまち)時代(じだい)(1336~1573)までは京都(きょうと)でもそう発音していました。
1603年に長崎(ながさき)で出版された「日葡(にっぽ)辞書(じしょ)(ポルトガル語(ご)の説明(せつめい)をつけた日本語(にほんご)辞書(じしょ))」をみると、
たとえば「祝儀(しゅうぎ)(祝(いわ)いまたは婚(こん)礼(れい))」「雑(ざっ)しょ(俗衆(ぞくしゅう)の間(あいだ)では、酒(さけ)や食物(しょくもつ)の贈物(おくりもの)のことをいう)」「手塩(てしお)皿(ざら)(塩(しお)を入(い)れて食膳(しょくぜん)に置(お)く塩入(しおいれ)皿(ざら)、または小皿(こざら))」「小取(こどり)(大(だい)工(く)の手(て)伝(つだ)い(い))」「移徙(わたまし)(新(ふたら)しい家(いえ)への移(い)転(てん))」「気張(きば)る(物事(ものごと)をするのに一層力(いっそうちから)を出(だ)す)」などが目(め)につき、
伊万里市のことばに当時(とうじ)の古語(こご)が残(の)っていることがわかります。
つづく

【むかしことば】編
「セ」を「シュ」と発音(はつおん)する人(ひと)は、だんだん少(すく)なくなりましたが、まだ、伊万里市(いまりし)の中高年(ちゅうこうねん)の人には、そう発音する人がいます。
九州地方(きゅうしゅうちほう)の人に特有(とくゆう)の発音といいますが、室町(むろまち)時代(じだい)(1336~1573)までは京都(きょうと)でもそう発音していました。
1603年に長崎(ながさき)で出版された「日葡(にっぽ)辞書(じしょ)(ポルトガル語(ご)の説明(せつめい)をつけた日本語(にほんご)辞書(じしょ))」をみると、
たとえば「祝儀(しゅうぎ)(祝(いわ)いまたは婚(こん)礼(れい))」「雑(ざっ)しょ(俗衆(ぞくしゅう)の間(あいだ)では、酒(さけ)や食物(しょくもつ)の贈物(おくりもの)のことをいう)」「手塩(てしお)皿(ざら)(塩(しお)を入(い)れて食膳(しょくぜん)に置(お)く塩入(しおいれ)皿(ざら)、または小皿(こざら))」「小取(こどり)(大(だい)工(く)の手(て)伝(つだ)い(い))」「移徙(わたまし)(新(ふたら)しい家(いえ)への移(い)転(てん))」「気張(きば)る(物事(ものごと)をするのに一層力(いっそうちから)を出(だ)す)」などが目(め)につき、
伊万里市のことばに当時(とうじ)の古語(こご)が残(の)っていることがわかります。
つづく

タグ :伊万里ふるさと読本より伊万里弁
2010年10月08日
正しい伊万里弁の使い方講座⑪
伊万里弁で語るバイのブログ
今日も正しい伊万里弁をマスターしましょう
【生活(せいかつ)の中(なか)でつかわれることば】編
わたしたちは人(ひと)と話(はな)す時(とき)に、相手(あいて)と自分(じぶん)がどのような人間関係(にんげんかんけい)にあるかということで、ことばづかいを変(か)えています。
目下(めした)や同格(どうかく)などは普通(ふつう)のことばで話しますが、目上(めうえ)に対(たい)する時は敬語(けいご)をつかいます。
たとえば「かれが来(き)ている」を「佐賀(さが)方言(ほうげん):あわいのきよらぁ・唐津(からつ)方言:あんわれんきょーらる(目下)」「佐賀方言:あいがきよー・唐津方言:ありがきょうる(同格から目下)」「佐賀方言:あふとんのきよらす(目上)」「佐賀方言:あんひとのきよんさぁ(目上)」「佐賀方言:あのおかたのきよいござぁ(かなり目上)」といいます。
「きよらぁ・きょーらる」は、もともと敬意(けいい)がこもっていたはずですが、現在(げんざい)は目下以外(いがい)にはつかいません。
終助詞(しゅうじょし)で丁寧(ていねい)さの度合(どあ)いをあらわすことばも多様(たよう)です。
断定(だんてい)の終助詞「~くさい」は「~くさん(同格)」「~くしゃー(目下)」「~くさんた(目上)」と変化(へんか)します。
強調(きょうちょう)・詠嘆(えいたん)の終助詞「~たい」は、変化形(けい)も多(おお)く、「~たー(目下)」「~たん(同格からやや目下)」「~たんにゃー(かなり目下)」「~たいのまい(「~たい」の丁寧語(ていねいご))」「~たいえー(やや非難(ひなん)の意味(いみ)がこもる。)」があります。
また「~たい」は、ほとんど敬意を含(ふく)まないので、上(うえ)に「~です」をつけた「~ですたい」ということばも作られました。
つづく

【生活(せいかつ)の中(なか)でつかわれることば】編
わたしたちは人(ひと)と話(はな)す時(とき)に、相手(あいて)と自分(じぶん)がどのような人間関係(にんげんかんけい)にあるかということで、ことばづかいを変(か)えています。
目下(めした)や同格(どうかく)などは普通(ふつう)のことばで話しますが、目上(めうえ)に対(たい)する時は敬語(けいご)をつかいます。
たとえば「かれが来(き)ている」を「佐賀(さが)方言(ほうげん):あわいのきよらぁ・唐津(からつ)方言:あんわれんきょーらる(目下)」「佐賀方言:あいがきよー・唐津方言:ありがきょうる(同格から目下)」「佐賀方言:あふとんのきよらす(目上)」「佐賀方言:あんひとのきよんさぁ(目上)」「佐賀方言:あのおかたのきよいござぁ(かなり目上)」といいます。
「きよらぁ・きょーらる」は、もともと敬意(けいい)がこもっていたはずですが、現在(げんざい)は目下以外(いがい)にはつかいません。
終助詞(しゅうじょし)で丁寧(ていねい)さの度合(どあ)いをあらわすことばも多様(たよう)です。
断定(だんてい)の終助詞「~くさい」は「~くさん(同格)」「~くしゃー(目下)」「~くさんた(目上)」と変化(へんか)します。
強調(きょうちょう)・詠嘆(えいたん)の終助詞「~たい」は、変化形(けい)も多(おお)く、「~たー(目下)」「~たん(同格からやや目下)」「~たんにゃー(かなり目下)」「~たいのまい(「~たい」の丁寧語(ていねいご))」「~たいえー(やや非難(ひなん)の意味(いみ)がこもる。)」があります。
また「~たい」は、ほとんど敬意を含(ふく)まないので、上(うえ)に「~です」をつけた「~ですたい」ということばも作られました。
つづく

タグ :伊万里ふるさと読本より伊万里弁
2010年10月07日
正しい伊万里弁の使い方講座⑩
伊万里弁で語るバイのブログ
今日も正しい伊万里弁をマスターしましょう
【男女(だんじょ)のことば】編
現在(げんざい)、女性(じょせい)のことばが荒(あら)っぽくなったといわれていますが、これは必(かなら)ずしも現在だけのことではありません。
市内(しない)の農村部などでは、日常(にちじょう)の会話(かいわ)で男女(だんじょ)のことばに大(おお)きな違(ちが)いはありませんでした。
しかし女性が少(すこ)しあらたまって話(はなし)をしなければならない時(とき)には、丁寧(ていねい)な話(はな)し方(かた)をしていました。
伊万里町(いまりちょう)やその周辺部(しゅうへんぶ)では「~して差(さ)し上(あ)げる」を「~してみゃーする」という女性が多(おお)くいました。
「~してまいらする」が変化(へんか)した丁寧語(ていねいご)ですが、今(いま)ではほとんどすたれてしまいました。
伊万里市(いまりし)の女性のことばでおもしろいのに「あいどん」があります。「あれまあ」とでもいうような、驚(おどろ)いた時(とき)やあきれた時のことばです。
また「どがんすっちゅー(=どうすればいいの)」というのは、何(なに)か困(こま)ったことが起(お)こった時に思(おも)わず口(くち)にすることばです。
市外(しがい)の人にはネズミの鳴(な)き声(ごえ)のように聞(き)こえて、おもしろいそうです。
男性(だんせい)のことばは女性のことばにくらべて、年齢(ねんれい)や社会的地位(しゃかいてきちい)の上下関係(じょうげかんけい)による違いが多く、たとえば「あなた」を意味(いみ)することばだけで、「おまえさん(目上(めうえ))」「おっつぁん(同格(どうかく)からやや目上)」「おまん(同格やや目上)」「おまい(同格やや目下(めした))」「わいしゅー(同格)」「わい(目下)」「うん(かなり目下)」などがあります。
動作(どうさ)をあらわすことばでも、威勢(いせい)がいいように意味を強(つよ)めることばを頭(あたま)につけて「うっかんがす(=壊(こわ)す)」「きゃーくいだます(=だます)」「ほたくいなぐ(=放(ほう)り投(な)げる)」のような表現(ひょうげん)が多いことも男性のことばの特徴(とくちょう)です。
つづく

【男女(だんじょ)のことば】編
現在(げんざい)、女性(じょせい)のことばが荒(あら)っぽくなったといわれていますが、これは必(かなら)ずしも現在だけのことではありません。
市内(しない)の農村部などでは、日常(にちじょう)の会話(かいわ)で男女(だんじょ)のことばに大(おお)きな違(ちが)いはありませんでした。
しかし女性が少(すこ)しあらたまって話(はなし)をしなければならない時(とき)には、丁寧(ていねい)な話(はな)し方(かた)をしていました。
伊万里町(いまりちょう)やその周辺部(しゅうへんぶ)では「~して差(さ)し上(あ)げる」を「~してみゃーする」という女性が多(おお)くいました。
「~してまいらする」が変化(へんか)した丁寧語(ていねいご)ですが、今(いま)ではほとんどすたれてしまいました。
伊万里市(いまりし)の女性のことばでおもしろいのに「あいどん」があります。「あれまあ」とでもいうような、驚(おどろ)いた時(とき)やあきれた時のことばです。
また「どがんすっちゅー(=どうすればいいの)」というのは、何(なに)か困(こま)ったことが起(お)こった時に思(おも)わず口(くち)にすることばです。
市外(しがい)の人にはネズミの鳴(な)き声(ごえ)のように聞(き)こえて、おもしろいそうです。
男性(だんせい)のことばは女性のことばにくらべて、年齢(ねんれい)や社会的地位(しゃかいてきちい)の上下関係(じょうげかんけい)による違いが多く、たとえば「あなた」を意味(いみ)することばだけで、「おまえさん(目上(めうえ))」「おっつぁん(同格(どうかく)からやや目上)」「おまん(同格やや目上)」「おまい(同格やや目下(めした))」「わいしゅー(同格)」「わい(目下)」「うん(かなり目下)」などがあります。
動作(どうさ)をあらわすことばでも、威勢(いせい)がいいように意味を強(つよ)めることばを頭(あたま)につけて「うっかんがす(=壊(こわ)す)」「きゃーくいだます(=だます)」「ほたくいなぐ(=放(ほう)り投(な)げる)」のような表現(ひょうげん)が多いことも男性のことばの特徴(とくちょう)です。
つづく

タグ :伊万里ふるさと読本より伊万里弁
2010年10月06日
正しい伊万里弁の使い方講座⑨
伊万里弁で語るバイのブログ
今日も正しい伊万里弁をマスターしましょう。
【仕事のことば】編です。
農業(のうぎょう)や漁業(ぎょぎょう)をする人(ひと)たちを中心(ちゅうしん)に、気象(きしょう)に関(かん)することばが多(おお)くあります。
日照(ひで)りが続(つづ)いたあとで適量(てきりょう)の雨(あめ)が降(ふ)ると「よかうるうぇー(良(よ)いうるおい)」といいます。
強(つよ)く降れば「きしょくにゃ降らす(大変(たいへん)にお振りになる)」、日照りが強ければ「照(て)らす(お照りになる)」、降り止(や)まない時(とき)は、「いつまっでん止まっさん(いつまでもお止みにならない)」、また、降り止んで晴(は)れた時は(あからした(お明(あ)かりになった))というように、気象について敬語(けいご)をつかいます。
むかしの農業は現在(げんざい)にくらべて、天候(てんこう)の影響(えいきょう)をうける度(ど)合(あ)いが大(おお)きかったので、天候について関心(かんしん)が高(た)まったのは当然(とうぜん)です。
また、人間(にんげん)の力(ちから)がおよばない気象に、おそれやうやまいの気持(きも)ちを持(も)っていたからです。
漁業をする人は、陸上(りくじょう)で仕事(しごと)をする人にくらべ、天気の急激(きゅうげき)な変化(へんか)によって危険(きけん)な目(め)にあうことが多いのは、むかしも今(いま)も変(か)わりません。
したがって、たえず気象情報(じょうほう)に気をつけていますが、それだけではなく、その海域(かいいき)での雲(くも)や風(かぜ)や空(そら)の色(いろ)などを観察(かんさつ)して、経験的(けいけんてき)に天候を予想(よそう)しています。
商業(しょうぎょう)をする人でも、行商(ぎょうしょう)の人と大きな店(みせ)をかまえている人とではことばづかいが違(ちが)いました。商店(しょうてん)主(しゅ)やその家族(かぞく)は、おだやかな口調(くちょう)で丁寧(ていねい)な方言(ほうげん)をつかっていました。
窯業(ようぎょう)をする人には、その業界(ぎょうかい)だけで使う特殊(とくしゅ)なことばがあります。「トンパン」や「ボシ」などは実物(じつぶつ)を見(み)ないとわかりにくいことばです。
つづく

【仕事のことば】編です。
農業(のうぎょう)や漁業(ぎょぎょう)をする人(ひと)たちを中心(ちゅうしん)に、気象(きしょう)に関(かん)することばが多(おお)くあります。
日照(ひで)りが続(つづ)いたあとで適量(てきりょう)の雨(あめ)が降(ふ)ると「よかうるうぇー(良(よ)いうるおい)」といいます。
強(つよ)く降れば「きしょくにゃ降らす(大変(たいへん)にお振りになる)」、日照りが強ければ「照(て)らす(お照りになる)」、降り止(や)まない時(とき)は、「いつまっでん止まっさん(いつまでもお止みにならない)」、また、降り止んで晴(は)れた時は(あからした(お明(あ)かりになった))というように、気象について敬語(けいご)をつかいます。
むかしの農業は現在(げんざい)にくらべて、天候(てんこう)の影響(えいきょう)をうける度(ど)合(あ)いが大(おお)きかったので、天候について関心(かんしん)が高(た)まったのは当然(とうぜん)です。
また、人間(にんげん)の力(ちから)がおよばない気象に、おそれやうやまいの気持(きも)ちを持(も)っていたからです。
漁業をする人は、陸上(りくじょう)で仕事(しごと)をする人にくらべ、天気の急激(きゅうげき)な変化(へんか)によって危険(きけん)な目(め)にあうことが多いのは、むかしも今(いま)も変(か)わりません。
したがって、たえず気象情報(じょうほう)に気をつけていますが、それだけではなく、その海域(かいいき)での雲(くも)や風(かぜ)や空(そら)の色(いろ)などを観察(かんさつ)して、経験的(けいけんてき)に天候を予想(よそう)しています。
商業(しょうぎょう)をする人でも、行商(ぎょうしょう)の人と大きな店(みせ)をかまえている人とではことばづかいが違(ちが)いました。商店(しょうてん)主(しゅ)やその家族(かぞく)は、おだやかな口調(くちょう)で丁寧(ていねい)な方言(ほうげん)をつかっていました。
窯業(ようぎょう)をする人には、その業界(ぎょうかい)だけで使う特殊(とくしゅ)なことばがあります。「トンパン」や「ボシ」などは実物(じつぶつ)を見(み)ないとわかりにくいことばです。
つづく

タグ :伊万里ふるさと読本より伊万里弁
2010年10月04日
知っとらす?【其之拾壱】
伊万里弁で語るバイのブログ
知っとらす? 第11弾!
早速ばってん・・・此方のえべっさん!
何処のえべっさんでっしゃろか?
何処のえべっさんでっしゃろか?

ヒントはばいね・・・

このえべっさんは毎日、元気か赤ちゃんの泣声ば聞きよらすえべっさん・・・
正解は・・・
» 続きを読む2010年09月30日
正しい伊万里弁の使い方講座⑧
伊万里弁で語るバイのブログ

伊万里市内のことばの違い④

昨日の続きです。
二里(にり)町(旧有田(ありた)郷)は、大体(だいたい)、西松浦郡(にしまつうらぐん)有田町・西有田町(現在は有田町と合併(がっぺい))の方言と同じです。
しかし、有田町の皿山(さらやま)と呼ばれる地域(ちいき)とは少し違(ちが)います。
旧有田郷でも二里町北部(ほくぶ)は伊万里に近(ちか)く、人の行(い)き来(き)も多かったので、伊万里町のことばと共通(きょうつう)するものがあります。
たとえば、「あんた」を、二里町南部(なんぶ)では「おっつぁん」というのに対し、北部では伊万里町と同じく「おまん」といいます。
東山(ひがしやま)代(しろ)町(旧山代郷)でも伊万里町(旧伊万里郷)に近い日(ひ)尾(お)地区では、「おまん」といい、少し遠(とお)い脇野(わきの)地区では「おっつぁん」といいます。
このように一口(ひとくち)に伊万里市のことばといっても、音韻(おんいん)の変化や語法(ごほう)のこまかい点(てん)では、地域によって違いがあります。
以上、「伊万里市内のことばの違い」でした。

タグ :伊万里ふるさと読本より伊万里弁